 室津と北野山(現在奈良市)と、桐山は、昔から大変仲の良い村でした。地続きで家々の付き合いも多く、氏神は桐山に社(郷社)を設け、祭りには三か村から桐山の宮にお渡りをして来たのでした。
室津と北野山(現在奈良市)と、桐山は、昔から大変仲の良い村でした。地続きで家々の付き合いも多く、氏神は桐山に社(郷社)を設け、祭りには三か村から桐山の宮にお渡りをして来たのでした。
ところが、いつのことか、お宮に備えつけてあった湯釜のことから争いが起き、それから郷社を解消して、争いの原因となった湯釜を、布目の大川に投げ込んでしまいました。
昔のことですから、どんな原因だったのかわかりませんが、祭礼の時、渡り衆を清める神聖な祭器である湯釜を、無きものにするほどですから、大変な紛争だったのでしょう。
湯釜を投げ込んだ川はたちまち変じて、大きな渦巻く淵となったというのです。これが釜淵の名の起こりです。
一説には、当時の祭神、九頭大明神の黄金の鍋つかみがあって、そのことから三か村の争いが起こったとも言われています。
今、桐山の神社には湯釜があり、永正十一年(一五一四)の銘が入っていますが、紛争の時のものであるかどうかはわかりません。
湯釜紛争があってから、お上(藩主)は、二度とこんな紛争が起こらぬよう「三か村縁組を禁ずる(縁組みご法度)」という厳しい禁令を敷きました。封建村落取り締まりの最後の手段だったとみられます。
これも氏神の神意によるものとか、破るとたたりがあるとか言われ、そのお仕置きは「縁を切る」とか「二度と敷居をまたいではいけない」とか、非常にきついものでした。
三か村では、それぞれ別に戸隠神社(手力男命)を造り、祭礼も神役も同じように行うようになりました。長い年月、縁が切れると、村同士は互いに疎遠になり、付き合いも少なくなりました。何回か復縁を話し合ったのですが、合意に達しなかったようです。
明治以降はそのご法度もなくなり、縁組みも復活して、幸せな家庭生活が行われるようになりました。
現在、老人たちも、室津、松尾、桐山で「三寿会」を結成し、交際を広める良き時代となりましたが、考えてみると、実に不幸な時代を経て来たのでした。



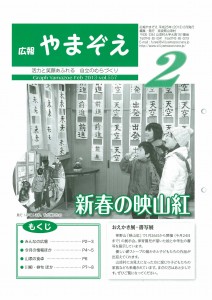
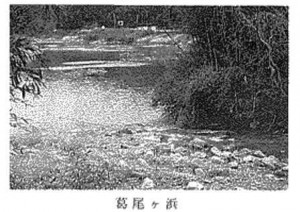 川沿いにあった昔の道は、名張のまちから木津へ、そこから北の京都へ通じる道でした。
川沿いにあった昔の道は、名張のまちから木津へ、そこから北の京都へ通じる道でした。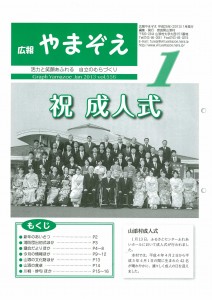
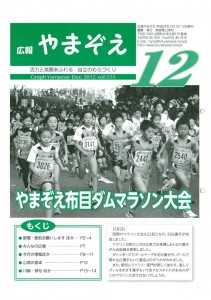
 この里は、蓮の花びらのような形をした山々に取り囲まれていて、なんとなく落ち着いついた感じがします。また、里の真ん中を西から東へと一筋のきれいな川が流れており、その北側には家々がきちんと南向きに立ち並んでいます。
この里は、蓮の花びらのような形をした山々に取り囲まれていて、なんとなく落ち着いついた感じがします。また、里の真ん中を西から東へと一筋のきれいな川が流れており、その北側には家々がきちんと南向きに立ち並んでいます。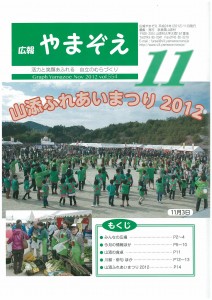
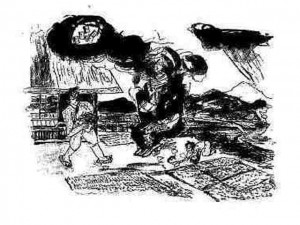 ある秋のことです。大夕立があって、庭に干してあった籾がすっかり流されてしまいました。家の中で一心に本を読んでいた新八良は大雨に気づかず、籾の片付けを忘れていたのです。
ある秋のことです。大夕立があって、庭に干してあった籾がすっかり流されてしまいました。家の中で一心に本を読んでいた新八良は大雨に気づかず、籾の片付けを忘れていたのです。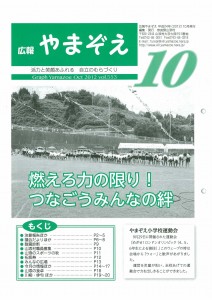
 いつごろ造られ、なにの塚であったのかなどは、一切わかっていません。今は荒れ果てて、村人からは忘れ去られようとしています。ところがここに伝わる伝説として「毎年元旦の晨(朝)、この塚の上で金色の鶏が東の空高く鳴く」と伝えられています。
いつごろ造られ、なにの塚であったのかなどは、一切わかっていません。今は荒れ果てて、村人からは忘れ去られようとしています。ところがここに伝わる伝説として「毎年元旦の晨(朝)、この塚の上で金色の鶏が東の空高く鳴く」と伝えられています。