| 目次 | ページ | |
|---|---|---|
| 平成21年度決算について | 2〜3 |  |
| 財政健全化判断比率について | 4 | |
| 議会だより ほか | 5〜8 | |
| パソコンのリサイクルについて | 9 | |
| 社会保険料控除証明書について ほか | 10 | |
| みんなの広場 | 11〜12 | |
| 今月の情報 ほか | 13〜16 |
平成22年10月号 Vol.529
掲載日付:2010年10月1日


掲載日付:2010年10月1日
掲載日付:2010年9月1日
昔、神野山は、天狗が住んでいる杉の木が一本生えているだけで、禿げ山だったそうです。一方、伊賀の国にある青葉山は、緑が豊かで、たくさんの草木が生い茂り、その間に奇岩もたくさんあって「庭園」のようだったそうです。
そして、神野山と青葉山には、それぞれ天狗が住んでいて、互いにたいそう仲が悪かったようで、いつもけんかばかりしていたそうです。
 あるとき、二人の天狗は、ささいなことから、物を投げ合うけんかを始めたそうで、青葉山の天狗はたいへん怒って、草木や岩を手当たり次第に神野山へ投げてきたそうです。
あるとき、二人の天狗は、ささいなことから、物を投げ合うけんかを始めたそうで、青葉山の天狗はたいへん怒って、草木や岩を手当たり次第に神野山へ投げてきたそうです。
けんかが終って見ると、青葉山はもとの草木や岩がなくなり、禿げ山となって、神野山は飛んできた岩で鍋倉渓ができて、山の頂上に至るまで草木が生い茂るようになりました。
そして、九十八夜のころになると、つつじの花が、山頂に咲きみだれるようになったそうです。
掲載日付:
掲載日付:2010年8月1日
大和と伊賀の国境近くに神野山があります。そんなに高くないが、こんもりとした松と、つつじがいっぱいの山で、その山の東北のふもとの所に鍋倉渓があります。
めずらしい谷で、600メートルにわたり、谷いちめん真っ黒い大きな岩がるいるいと重なり合ってつらなっています。その岩の下には、かなりの水が川になり、石にぶつかっていて、水の音は聞こえますが、水はちっとも見えません。伏流水なのです。ところが、その真ん中どころにある平べったい石に腹ばって下をのぞくと、きれいな水が流れていて、じっと見つめると、死んだ親の顔がはっきり見られるというのです。それも正直な人だけに見えるのだと言われます。どうしてそんな伝えが起こったのでしょうか。
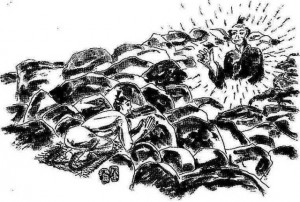 むかし、この近くの村に、年寄りの父親と、若い息子が住んでいました。
むかし、この近くの村に、年寄りの父親と、若い息子が住んでいました。
家が貧しかったので、若い男は山しごとや畑しごとにやとわれたり、奈良の町へ使い走りを頼まれたりしてくらしていました。まじめで、正直で、うらおもてがなくよく働いたので、村人の受けもよく、とくに奈良の町への使い走りをよく頼まれました。
はやくて、まちがいがなく、相手の手紙や荷物をとどけてくれると、頼み手はよろこんで、駄ちんをはずんでくれたそうな。
そんな時、若い男は、奈良の店やのおいしいものを買ってきて、自分は食べず「おっ父、腹いっぱい食べや」と言って食べさせるのでした。
親せきはなく、身寄りといえば父親ひとりきりのせいもあるが、とてもやさしく、父親を大事にして、夜は足をもんだりしていました。
「すまんのう」と言う親に、
「なに言うとんね、おっ父、元気になぁ」と言うのでした。
村人たちは「今どきめずらしい親孝行で、感心な男や」とほめていました。
ところがある時、その大事な父親が風邪で寝込んでしまい、目に見えて弱ってきたのです。
心配のあまり若い男は、毎日薬を奈良の店で買ってきて、父親に飲ませました。そして鍋倉渓の石の上にすわって、東からあがる月をおがみ「おっ父の病気をなおして下さいませ」とお祈りをするのでした。
しかし、その甲斐もなく父親は、はかなく死んでしまいました。
若い男のなげきは大変なものでした。村人たちは見かねて「もう年やから、あきらめるよりほかない」と、なぐさめましたが、死んだ父親を思い出すとじっとしていられず、そのたびごとに鍋倉渓へやってきては、平べったい石の上にすわって涙ぐんでいました。
ある月の夜、石の上で若い男はたまりかねて、
「おっ父、今、どこで、どないしとるんや、会いたいのう」と大きな声を出しました。そうしたら、すわっていた平べったい石がぐらっとゆらいだのです。思わず石の上に腹ばいになって、何気なく、底に流れる澄みきった水を眺めた男は、突然「おっ父、おっ父よ」とうれしそうに叫んだのです。
なんと、にっこりほほえんだ父親の顔が、水の中にありありと見えたのでした。
これが「鍋倉渓の親の顔」の伝えの始まりです。
掲載日付:
掲載日付:2010年7月1日
的野と、松尾や峰寺の「押谷」を結ぶ一本の山道があります。現在は広い道路が別の場所につけられ、車の利用も多くなったのでこの山道はほとんど使われていません。山道と言っても、旧東山村が山添村になるまでは、村人が役場等へ用事でいく場合はもちろんのこと、大字間の往来に、また学校、保育園への子供の通学に、なくてはならない重要な道路でありました。
 その道程の中程に「嫁取り神」という所があります。そのあたりは、道の両脇に大木がうっそうと茂っていて、昼でもほの暗い、薄気味悪いような所です。子供がそこを通る時には、恐ろしさを感じて、一目散に走り抜けていました。
その道程の中程に「嫁取り神」という所があります。そのあたりは、道の両脇に大木がうっそうと茂っていて、昼でもほの暗い、薄気味悪いような所です。子供がそこを通る時には、恐ろしさを感じて、一目散に走り抜けていました。
その昔「嫁入り」がここを通った時、お嫁さんが突然何物かにさらわれて、消え失せてしまうという恐ろしいことが起こったそうです。
それから後、村人はそこを「嫁取り神」と呼ぶようになり、同じことが二度と起きることを恐れて、まわり道をしてお嫁入りしたそうです。
掲載日付:
掲載日付:2010年6月1日
掲載日付:
村の中央の高いところに、八王子神社があります。「助命(ぜみょう)の村に過ぎたるものは宮の社段か、般若の倉か、尚も与平治の道楽か」と唄われたとおり、100メートル余りもある高い石段があり、下からお社を見上げると、ずいぶん高い所にあってその周囲をこんもりとした森がかこんでいます。
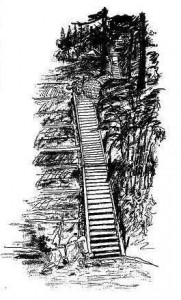 大正の初めまでは、直径1メートル余りもある大きい杉や松がありましたが、台風で倒れたり、松喰い虫の被害や、古損木となったりして、今はそんな大木ではありませんが、それでも森の森厳さは保たれて神々しいお宮さんです。
大正の初めまでは、直径1メートル余りもある大きい杉や松がありましたが、台風で倒れたり、松喰い虫の被害や、古損木となったりして、今はそんな大木ではありませんが、それでも森の森厳さは保たれて神々しいお宮さんです。
その昔、この石段には、時おり夕方になると、「しんぐりまくり」というあやしい者が来て、しんぐりをまくる(ころがす)ことがあるといって恐れられていました。
「しんぐり」とは、竹で編んで魚を入れるかごで、魚取りにはなくてはならないものです。そのしんぐりの中には、いたずら小僧が入れられていると言うのです。
こんなしんぐりに入れられて、高い石段からころがされると、どんなになってしまうのか、わかりきったことです。
そこでこの地方では、子どもがいたずらをすると、「それ、また、しんぐりまくりがやってくるぞ」と言っておどかしますから、子どもはおとなしくなるというのです。
掲載日付:2010年5月1日