| 目次 | ページ | |
|---|---|---|
| 地上デジタル放送の準備はお済ですか? | 2 | 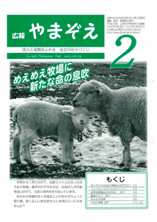 |
| 『e-Tax』ならこんなにいいこと | 3 | |
| 住所変更届出はお早めに ほか | 4 | |
| 議会だより ほか | 5 | |
| みんなの広場 | 6 | |
| 今月の情報 ほか | 7〜10 |
平成23年2月号 Vol.533
掲載日付:2011年2月1日


掲載日付:2011年2月1日
掲載日付:
昔から、天守山のふもとに十数戸の集落があった。これが菅生の草分けの地“大垣内”なんや。
ここに、すばらしく美しい娘が育っておった。時々天守山城にお成りのお殿様に聞こえぬはずがない。やがて召されて、お殿様のお嫁さんになった。
 さて、そのお嫁さん、お腹が大きなってきたころ、おならはずしはったらしい。「ブウー」とな。すると、お殿さん「いてらん、いね」って追い出してしまわはった。いんでから、お嫁さんに赤ん坊が生まれた。赤ん坊はすくすく育って、よっぽど大きくなったころ、「お母さん、みんなだれでもお父はんあるのに、私にはお父はんあらへん、どういうわけや」ちゅうて母親に聞いたらしい。お母さんは返事に困ったけど、思い切って話してやらはった。「恥ずかしい話やけど、お前がお腹にいる時にな、おならはずしてしもて、それで追い出されてしもたんや」-と。
さて、そのお嫁さん、お腹が大きなってきたころ、おならはずしはったらしい。「ブウー」とな。すると、お殿さん「いてらん、いね」って追い出してしまわはった。いんでから、お嫁さんに赤ん坊が生まれた。赤ん坊はすくすく育って、よっぽど大きくなったころ、「お母さん、みんなだれでもお父はんあるのに、私にはお父はんあらへん、どういうわけや」ちゅうて母親に聞いたらしい。お母さんは返事に困ったけど、思い切って話してやらはった。「恥ずかしい話やけど、お前がお腹にいる時にな、おならはずしてしもて、それで追い出されてしもたんや」-と。
それを聞いた子は、「そうですか…、そんならわし、ちょっと明日から…。お弁(弁当)炊いて下さい」と言うと、次の日、どこへやら出かけて行ったそうな。殿様の屋敷近くでは、「屁の種いりまへんかぁー、屁の種いりまへんかぁー、屁の種売りますー」と、毎日さけび歩く者があるんじゃと。そのうちお殿様の耳に入って、「もしや、これは吾子では…。吾子に間違いない」と勘付かはったらしい。
そこで、その子を呼んでお殿様は、「五万石やるから下がれ」とおっしゃったそうな。しかしその子は返事をしない。お殿様はまた「五万石やるから下がれ」とくり返し三回おっしゃった時、「はい、ありがとうございます」ちゅうたと。
いよいよ五万石の金子をお殿様がやろうとしゃっはったら、「ちょっと待って下さい。お殿さんちゅうもんは、一言はっちゃ言わんもんなのに、三言もおっしゃった。よって、三、五、十五万石もらわななりまへん」と言って聞かない。
あんじょう理屈に詰まってしもうて、十五万石もらい、そしてお殿さんの座におさまったんじゃと。
掲載日付:2011年1月1日
掲載日付:
掲載日付:
ずっと昔からこの地に、腰越の竹倉の森と、対岸峰寺領内の天王の森の白藤が生い茂り、両方から伸びた蔓が絡み合う時、「神と人間の中間にある大力人があらわれる」という言い伝えがありました。
 何百年か前、蔓の絡み合いがあって、大力与門太夫が誕生したのです。これから、与門太夫の大力ぶりをお話ししましょう。与門太夫が隣村桃香野へ夜遊びに行き、村の若い衆とけんかをした帰り、石の橋三枚をめくり上げ、一荷にして持ち帰り、深江橋の上にひとりで抱え渡したのです。
何百年か前、蔓の絡み合いがあって、大力与門太夫が誕生したのです。これから、与門太夫の大力ぶりをお話ししましょう。与門太夫が隣村桃香野へ夜遊びに行き、村の若い衆とけんかをした帰り、石の橋三枚をめくり上げ、一荷にして持ち帰り、深江橋の上にひとりで抱え渡したのです。
今の唐戸橋の位置で、神業のような大力。桃香野から、橋の石を返すよう迫ってきた時、ほしかったら持って帰れと言い返したが、残念ながら重くて持ち帰ることができなかったそうです。
明治の中ごろ、橋の改良から橋の石がいらなくなったので、峰寺の人々が総出で綱をつけて曳きながら、峰寺の神社前の小川の橋に架けかえたのでした。石は一本の長さ約3メートル、幅約45センチメートルほどで、重さは1トンはあります。
ある時、青竹8束を担いで奈良へ買い物に行きました。桐山の尻打坂まで行った時、上から西上のおばあさんが、「与門太夫さん、奈良へ行くのやったら、小豆8斗を売って、塩を買ってきておくれ」と頼みました。与門太夫は、小豆8斗の袋を竹の上にのせて歩きました。
春日山を9分どおり下った所に休み場があって、若い衆が大勢相撲を取っていました。肩の荷をおろして相撲を見物していましたが、おもしろくて、つい大笑いしてしましました。若い衆は不機嫌になって、「笑うのであれば、相撲を取ってみよ、見せてもらうで」と言ったので、「よーし」と立ち上がり、担いできた青竹の太いのを引き抜いて、親指と人差し指でパーシ、パーシと竹の節を押しつぶし、その竹でまわしを締めて「さあ、こい」と土俵に立ちました。
若い衆で相手になる者はなく「春日奥山の天狗さんが出た」と急いで散って行ってしまったのです。それ以来、春日山の相撲はなくなったとのことです。竹倉の姓の起こりとも伝えられます。
あずかった小豆を売って、その代金で買った塩は、西上の家へ持っていったのですが、表の縁にドンとおろしたところ、大量の塩が重たくて縁が落ちたと言います。
ある時薪柴がなくなったので、朝、暗いうちに起きて家を出たところ、鎌の柄と思って、石臼の挽木を腰に差して行き、仕方なく挽木を斧と鎌のかわりに使って、柴をたたきちぎって家へ持って帰りました。その量は門いっぱいに山のように積まれたと言います。
昔の道は歩くだけの広さで、荷車も通らず、馬の背に荷物を振り分けて運んだのです。川には簡単な板橋しかなく、雨が降れば板橋が流されました。そんな時、与門太夫は馬の背に荷物を積んだまま、馬の両足4本を抱き上げて、らくらくと向こう岸へ渡したと言います。
大字松尾、瑞徳家の周辺は昔からの竹林でした。茶園にするため、与門太夫に請け負ってもらったのですが、毎日毎日ドンドをして仕事をしません。「与門太夫さん、いつ仕事をはじめてくれますか」と尋ねたところ、与門太夫は早速と竹薮へ入り、片っぱしから竹を抱きかかえて根っこから引き抜いていったので、開墾はまことに早く見事に完成したのでした。
唐戸橋から腰越へ向かう100メートルの所に、与門太夫の風呂場跡があります。焚口の柱石、笠石が自然石で組まれています。
与門太夫が世を去る時、「わしのことは歴史に残さないで、後に力士があらわれてくるから、その者を留めよ」と言い残したそうです。
その後村人たちは、大力持ちの出現を恐れて両方の森を切りはらったので、大力人は与門太夫だけで終わったのでした。
当地にはフジノミ(藤の実)、藤本、石橋などの地名や家名が残っていて、当時のようすをわずかに伝えています。
掲載日付:2010年12月1日
毛原の里を流れる川を笠間川と言います。その川筋に「鐘ヶ淵」という深い淵があります。そしてそこには急な山が迫っていますが、その山の頂には、むかし古い鐘楼が建っていたので、そこを「カネツキドウ」と呼んでいます。
さて、むかしむかしのある晩のこと、どうしたはずみかその鐘楼がこわれて、吊るしてあった大きな釣り鐘が、“どすん”と大きな音をたてて落ち、ごろごろころげて鐘ヶ淵に沈んでしまいました。 ところがこの淵には、昔から長い間住みついていた不思議な竜がおりました。この竜は、水の中ではこわいものなしで、たいへん威張っていました。だから、気に入らないことがあると、すぐ腹を立て、洪水を起こして田畑や橋を流したり、時には、家や人の命までもうばってしまうほどの乱暴者だったのです。
ところがこの淵には、昔から長い間住みついていた不思議な竜がおりました。この竜は、水の中ではこわいものなしで、たいへん威張っていました。だから、気に入らないことがあると、すぐ腹を立て、洪水を起こして田畑や橋を流したり、時には、家や人の命までもうばってしまうほどの乱暴者だったのです。
でも、この暴れん坊には、ただひとつの頭のあがらない怖いものがあったのです。それは鉄などの金物でした。
ちょうど真夜中のことだったので、ぐっすり寝こんでいた竜の枕元へ、突然だいきらいな釣り鐘がどしーんと飛び込んできたものですから、さあ大変。竜はあわてて、命からがら逃げました。川の下流に「権蛇淵」という淵がありますが、ここで蛇の姿に変身して、しばらくの間岩の穴にひそんでいたのです。
ところがそこは、同じ川筋なので、いつまた恐ろしい釣り鐘が追っかけて来るかもしれません。びくびくしながら思案の末、いっそうのこと高い山から天に昇ろうと決心しました。幸いにも、川のすぐそばには青葉の山々が迫っていて、大昔に噴火した「茶臼山」がそびえています。そしてその山からも、谷伝いに水が流れています。
「よしっ」と決心した竜は、水を伝って上へ上へと登りました。途中で少し疲れたので休みました。そこを今も蛇谷と呼んでいます。休んでは登り、休んでは登り、竜はとうとう山の頂上まで逃げのびました。
不思議なことに、山のてっぺんからは赤い火が噴いて、黒い煙がいきおいよく立ち上っているではありませんか。竜は大喜びで、その煙に乗って天に昇って行きました。
ところで淵に沈んだ釣り鐘はどうなったでしょうか。あれから何千年たったかはしれませんが、今もそのまま鐘ヶ淵の底深く沈んでいるそうです。きっと鐘楼がこわれてなくなってしまったので、帰るところがないからなのでしょう。
そして不思議なことに、この鐘は、闇夜の晩に限って、ときどき淵の底からうなることがあるそうです。そんな時には、必ずこの地方に、何かよくないことが起きると言い伝えられています。
掲載日付:
掲載日付:2010年11月1日
神野山から大塩へ下る麓に4メートル四方の大岩があって、岩の上の20センチメートルぐらいの凹みに水がたまっています。この水はあふれることなく、全くなくなりもせず、いつも同じようにたまっています。
 むかし、弘法大師が北野村から神野山へ登られる時、この村の人たちが道案内をしました。
むかし、弘法大師が北野村から神野山へ登られる時、この村の人たちが道案内をしました。
大岩の所で弘法大師が村人に言いました。
「何か困っていることはないかのう」
「はい、ここは山奥で、塩がないので困っています」
「それでは塩が出るようにしてやろう」
お大師さんは念仏を唱えながら、持っていた杖で大岩を二、三度ポンポンとたたきました。するとポコッと穴が開いて、中から塩水が湧いてきました。お大師さんは、塩水から取った塩を村人にわけあたえられました。
「この水は一日に何べんも増えたり減ったりするぞ。この水加減で、伊勢の海の潮の満ち干がわかる。また人の生き死にもわかるだろう」と言われました。
それから今日まで、大石の水は絶えたことがありません。岩が硯石のかっこうをしているので、村の人は大師の硯石と言って水を見ています。山添村の「大塩」という地名もそれから起こったと言います。
このあたり一帯に、むかしは岩塩が出たのかもしれません。近くに塩瀬地蔵が祀られているのも何かの縁だろうと言われています。
掲載日付:
掲載日付:2010年10月1日
その昔、神代の時代に「熯之速日命(ひのはやひのみこと)」という女神が伊勢に住んでおられました。多くの女神の中でもとびぬけて美しい女神であったので、男の神々が恋い慕い、われもわれもとつきまとったのです。
 あまり多くの男神に慕われた「ひのはやひのみこと」は、とてもみんなの好意にこたえられないと思い、ひとりこっそりと我が身をかくそうと、伊勢から熊野を通って、吉野の山中に住まいを定められたのでした。
あまり多くの男神に慕われた「ひのはやひのみこと」は、とてもみんなの好意にこたえられないと思い、ひとりこっそりと我が身をかくそうと、伊勢から熊野を通って、吉野の山中に住まいを定められたのでした。
女神を慕う男の神々は、どこまでもあとを追い、探しもとめてはつきまとったのです。思いあまった女神は、さらに北へ進み、大和は神野山の弁天池のほとりにひっそりと住まわれたのでした。
これで安心と思われた女神でしたが、男の神々の思いはおさまらず、われもわれもと女神を追い求めて神野山めがけてかけつけました。
たまりかねた女神は、その目をのがれようと一匹のオロチになられたのです。
女神を慕って、山また山を越えて来た男の神々の目の前に横たわる一匹のオロチ。これがあの美しい「ひのはやひの女神」とは、さすがの神々も思いもよらず、「おのれ行く手を邪魔するにっくきオロチめ」と、それぞれの剣をもってしとめてしまいました。するとオロチは、見る見るうちに美しい女神の傷ついた姿にかわり、弁天池の澄んだ水の中にその身を横たえたのでありました。
男の神々は、その痛ましい姿を見て涙の涸れるまで泣き明かしました。そして我が恋が実らず、その思いが女神をこんな姿にしてしまったことを悔い、なげき悲しみつつ、神野山山頂に女神の墓を造り、お祀りしたのでした。山頂の王塚にはこんな悲しい話が秘められているのです。
そしてまた、山一面に咲く紅つつじは、清らかな女神の色であるとも言われています。