ずっと昔からこの地に、腰越の竹倉の森と、対岸峰寺領内の天王の森の白藤が生い茂り、両方から伸びた蔓が絡み合う時、「神と人間の中間にある大力人があらわれる」という言い伝えがありました。
 何百年か前、蔓の絡み合いがあって、大力与門太夫が誕生したのです。これから、与門太夫の大力ぶりをお話ししましょう。与門太夫が隣村桃香野へ夜遊びに行き、村の若い衆とけんかをした帰り、石の橋三枚をめくり上げ、一荷にして持ち帰り、深江橋の上にひとりで抱え渡したのです。
何百年か前、蔓の絡み合いがあって、大力与門太夫が誕生したのです。これから、与門太夫の大力ぶりをお話ししましょう。与門太夫が隣村桃香野へ夜遊びに行き、村の若い衆とけんかをした帰り、石の橋三枚をめくり上げ、一荷にして持ち帰り、深江橋の上にひとりで抱え渡したのです。
今の唐戸橋の位置で、神業のような大力。桃香野から、橋の石を返すよう迫ってきた時、ほしかったら持って帰れと言い返したが、残念ながら重くて持ち帰ることができなかったそうです。
明治の中ごろ、橋の改良から橋の石がいらなくなったので、峰寺の人々が総出で綱をつけて曳きながら、峰寺の神社前の小川の橋に架けかえたのでした。石は一本の長さ約3メートル、幅約45センチメートルほどで、重さは1トンはあります。
ある時、青竹8束を担いで奈良へ買い物に行きました。桐山の尻打坂まで行った時、上から西上のおばあさんが、「与門太夫さん、奈良へ行くのやったら、小豆8斗を売って、塩を買ってきておくれ」と頼みました。与門太夫は、小豆8斗の袋を竹の上にのせて歩きました。
春日山を9分どおり下った所に休み場があって、若い衆が大勢相撲を取っていました。肩の荷をおろして相撲を見物していましたが、おもしろくて、つい大笑いしてしましました。若い衆は不機嫌になって、「笑うのであれば、相撲を取ってみよ、見せてもらうで」と言ったので、「よーし」と立ち上がり、担いできた青竹の太いのを引き抜いて、親指と人差し指でパーシ、パーシと竹の節を押しつぶし、その竹でまわしを締めて「さあ、こい」と土俵に立ちました。
若い衆で相手になる者はなく「春日奥山の天狗さんが出た」と急いで散って行ってしまったのです。それ以来、春日山の相撲はなくなったとのことです。竹倉の姓の起こりとも伝えられます。
あずかった小豆を売って、その代金で買った塩は、西上の家へ持っていったのですが、表の縁にドンとおろしたところ、大量の塩が重たくて縁が落ちたと言います。
ある時薪柴がなくなったので、朝、暗いうちに起きて家を出たところ、鎌の柄と思って、石臼の挽木を腰に差して行き、仕方なく挽木を斧と鎌のかわりに使って、柴をたたきちぎって家へ持って帰りました。その量は門いっぱいに山のように積まれたと言います。
昔の道は歩くだけの広さで、荷車も通らず、馬の背に荷物を振り分けて運んだのです。川には簡単な板橋しかなく、雨が降れば板橋が流されました。そんな時、与門太夫は馬の背に荷物を積んだまま、馬の両足4本を抱き上げて、らくらくと向こう岸へ渡したと言います。
大字松尾、瑞徳家の周辺は昔からの竹林でした。茶園にするため、与門太夫に請け負ってもらったのですが、毎日毎日ドンドをして仕事をしません。「与門太夫さん、いつ仕事をはじめてくれますか」と尋ねたところ、与門太夫は早速と竹薮へ入り、片っぱしから竹を抱きかかえて根っこから引き抜いていったので、開墾はまことに早く見事に完成したのでした。
唐戸橋から腰越へ向かう100メートルの所に、与門太夫の風呂場跡があります。焚口の柱石、笠石が自然石で組まれています。
与門太夫が世を去る時、「わしのことは歴史に残さないで、後に力士があらわれてくるから、その者を留めよ」と言い残したそうです。
その後村人たちは、大力持ちの出現を恐れて両方の森を切りはらったので、大力人は与門太夫だけで終わったのでした。
当地にはフジノミ(藤の実)、藤本、石橋などの地名や家名が残っていて、当時のようすをわずかに伝えています。
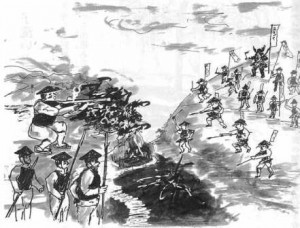 敵将、後藤又兵衛は大軍をもって布陣。味方の軍はすでに浮足立って苦戦の時、源太夫は、敵の大将さえ討ち取れば、味方の勝利につながると思い、又兵衛を探しましたが混戦の中でなかなか見つかりません。
敵将、後藤又兵衛は大軍をもって布陣。味方の軍はすでに浮足立って苦戦の時、源太夫は、敵の大将さえ討ち取れば、味方の勝利につながると思い、又兵衛を探しましたが混戦の中でなかなか見つかりません。


 ◎カンノ谷のしんぐりまくり
◎カンノ谷のしんぐりまくり ◎三ヶ谷の伝え
◎三ヶ谷の伝え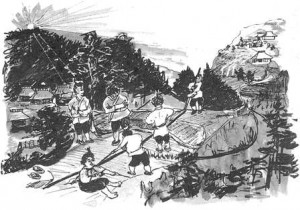 昔、的野と、隣接する現在の奈良市水間町との村境が定かでなかったころ、両方の村人の間ではいろいろと争いが絶えず、両村は不仲になって久しく縁組もなかったそうです。そこで、争い事のもとになる境界の取り決めに、よい方法はないものかと思案のあげく、一つのよい案を考え出しました。
昔、的野と、隣接する現在の奈良市水間町との村境が定かでなかったころ、両方の村人の間ではいろいろと争いが絶えず、両村は不仲になって久しく縁組もなかったそうです。そこで、争い事のもとになる境界の取り決めに、よい方法はないものかと思案のあげく、一つのよい案を考え出しました。 昔の茶摘みといえば、絣のはっぴにすげの笠、赤いたすきをかけたきれいな“摘み娘さん”たちが、10人も20人も茶山に出かけます。
昔の茶摘みといえば、絣のはっぴにすげの笠、赤いたすきをかけたきれいな“摘み娘さん”たちが、10人も20人も茶山に出かけます。 さて、そのお嫁さん、お腹が大きなってきたころ、おならはずしはったらしい。「ブウー」とな。すると、お殿さん「いてらん、いね」って追い出してしまわはった。いんでから、お嫁さんに赤ん坊が生まれた。赤ん坊はすくすく育って、よっぽど大きくなったころ、「お母さん、みんなだれでもお父はんあるのに、私にはお父はんあらへん、どういうわけや」ちゅうて母親に聞いたらしい。お母さんは返事に困ったけど、思い切って話してやらはった。「恥ずかしい話やけど、お前がお腹にいる時にな、おならはずしてしもて、それで追い出されてしもたんや」-と。
さて、そのお嫁さん、お腹が大きなってきたころ、おならはずしはったらしい。「ブウー」とな。すると、お殿さん「いてらん、いね」って追い出してしまわはった。いんでから、お嫁さんに赤ん坊が生まれた。赤ん坊はすくすく育って、よっぽど大きくなったころ、「お母さん、みんなだれでもお父はんあるのに、私にはお父はんあらへん、どういうわけや」ちゅうて母親に聞いたらしい。お母さんは返事に困ったけど、思い切って話してやらはった。「恥ずかしい話やけど、お前がお腹にいる時にな、おならはずしてしもて、それで追い出されてしもたんや」-と。 何百年か前、蔓の絡み合いがあって、大力与門太夫が誕生したのです。これから、与門太夫の大力ぶりをお話ししましょう。与門太夫が隣村桃香野へ夜遊びに行き、村の若い衆とけんかをした帰り、石の橋三枚をめくり上げ、一荷にして持ち帰り、深江橋の上にひとりで抱え渡したのです。
何百年か前、蔓の絡み合いがあって、大力与門太夫が誕生したのです。これから、与門太夫の大力ぶりをお話ししましょう。与門太夫が隣村桃香野へ夜遊びに行き、村の若い衆とけんかをした帰り、石の橋三枚をめくり上げ、一荷にして持ち帰り、深江橋の上にひとりで抱え渡したのです。 ところがこの淵には、昔から長い間住みついていた不思議な竜がおりました。この竜は、水の中ではこわいものなしで、たいへん威張っていました。だから、気に入らないことがあると、すぐ腹を立て、洪水を起こして田畑や橋を流したり、時には、家や人の命までもうばってしまうほどの乱暴者だったのです。
ところがこの淵には、昔から長い間住みついていた不思議な竜がおりました。この竜は、水の中ではこわいものなしで、たいへん威張っていました。だから、気に入らないことがあると、すぐ腹を立て、洪水を起こして田畑や橋を流したり、時には、家や人の命までもうばってしまうほどの乱暴者だったのです。 むかし、弘法大師が北野村から神野山へ登られる時、この村の人たちが道案内をしました。
むかし、弘法大師が北野村から神野山へ登られる時、この村の人たちが道案内をしました。 あまり多くの男神に慕われた「ひのはやひのみこと」は、とてもみんなの好意にこたえられないと思い、ひとりこっそりと我が身をかくそうと、伊勢から熊野を通って、吉野の山中に住まいを定められたのでした。
あまり多くの男神に慕われた「ひのはやひのみこと」は、とてもみんなの好意にこたえられないと思い、ひとりこっそりと我が身をかくそうと、伊勢から熊野を通って、吉野の山中に住まいを定められたのでした。